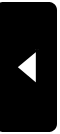傷害事件のおかげで
昨日の傷害虚偽事件はとんでもなく迷惑でした
「犯人が逃走中」のときは、テレビ番組の逃走中好きなムクも怖がり

ウチに来るのではないかと何度も聞き、登下校は車で送迎して欲しいとか留守番は無理とか、
落ち着かせるための条件探しに必死でした。
犯人が捕まったと知った今朝も「帰る時間には家に絶対いてね」と言い残して登校です
下校が引き渡しになったり、
行事の予定が変更されたり、
周囲が不安になるのを敏感に察知して
不安定になったお子さんもいるんじゃないかな。
児童館もプラザも利用停止になったので
先生付き添いで集団下校してくる子どもたちをみながら
仕事などの関係で子どもより先に帰れない家庭はどうするんだろう?と思いました。
こんな時のために、子どもの特性を知っている仲間や近所の人に
「もしもの時は、こうしよう」という話し合いをしておくのも大事だね。
ちなみに・・・
緊急連絡網メールが届いた時、私は
家から自転車で20分の場所にあるMams style(マムズスタイル)の事務局で打ち合わせをしていて、
猛ダッシュで自転車コギコギ帰ってきました
気持ちはザワザワしましたが、お陰でいい運動にはなりました

「犯人が逃走中」のときは、テレビ番組の逃走中好きなムクも怖がり


ウチに来るのではないかと何度も聞き、登下校は車で送迎して欲しいとか留守番は無理とか、
落ち着かせるための条件探しに必死でした。
犯人が捕まったと知った今朝も「帰る時間には家に絶対いてね」と言い残して登校です

下校が引き渡しになったり、
行事の予定が変更されたり、
周囲が不安になるのを敏感に察知して
不安定になったお子さんもいるんじゃないかな。
児童館もプラザも利用停止になったので
先生付き添いで集団下校してくる子どもたちをみながら
仕事などの関係で子どもより先に帰れない家庭はどうするんだろう?と思いました。
こんな時のために、子どもの特性を知っている仲間や近所の人に
「もしもの時は、こうしよう」という話し合いをしておくのも大事だね。
ちなみに・・・
緊急連絡網メールが届いた時、私は
家から自転車で20分の場所にあるMams style(マムズスタイル)の事務局で打ち合わせをしていて、
猛ダッシュで自転車コギコギ帰ってきました

気持ちはザワザワしましたが、お陰でいい運動にはなりました

おにーちゃん、変だって言われてるよ
ムクは登下校時に独り言を言いながら帰ってきます
小学生の頃からなので我が家にとってはフツウのこと。
中学生になって思春期を迎え、声のボリュームが大きくなったから
かなり離れたところを歩いてくるのが分かります

昨日も「あー、ムクちゃん、帰ってくるね」とユズに声をかけると
ユズが一言。
おにーちゃん、変って言われているよ。
どうやら近所の低学年の子に「一人で喋ってて変」と言われたらしい。
確かに、独り言を言わないで歩いている人から見れば、変かもね。
同年代の友達は、昔からそれが当たり前になっているから「変」なんて言わないし。
小さい頃から色々な人に知ってもらっていると
ムクの「変な行動」も変じゃなくなるんだろうな~
その独り言も、ここ最近はVS嵐じゃないんですよ。
この時期は「女子バレーボール」の実況しています。
今夜もテレビの実況が聞こえないくらい大きな声で実況する事でしょう・・・

小学生の頃からなので我が家にとってはフツウのこと。
中学生になって思春期を迎え、声のボリュームが大きくなったから
かなり離れたところを歩いてくるのが分かります


昨日も「あー、ムクちゃん、帰ってくるね」とユズに声をかけると
ユズが一言。
おにーちゃん、変って言われているよ。
どうやら近所の低学年の子に「一人で喋ってて変」と言われたらしい。
確かに、独り言を言わないで歩いている人から見れば、変かもね。
同年代の友達は、昔からそれが当たり前になっているから「変」なんて言わないし。
小さい頃から色々な人に知ってもらっていると
ムクの「変な行動」も変じゃなくなるんだろうな~
その独り言も、ここ最近はVS嵐じゃないんですよ。
この時期は「女子バレーボール」の実況しています。
今夜もテレビの実況が聞こえないくらい大きな声で実況する事でしょう・・・
東田直樹さんの講演会にて
会いたいと思っていた方に会えました。
東田直樹さん。
書籍「自閉症の僕が跳びはねる理由―会話のできない中学生がつづる内なる心 」
」
を知ったのはかなり前で、ムクのできなさに落ち込んでいた時期。
重度って言ってもこんな文章を書けるなら軽い方なんだじゃないの?
と。勝手に思い込み読みませんでした。
昨年のNHKドキュメンタリーを観て、なんていう勘違いをしていたのだと反省し、
次の日に「自閉症の僕が跳びはねる理由―会話のできない中学生がつづる内なる心 」
」
を購入して読み、涙が止まりませんでした
会いたいな・・・と思っていたら同じように思ってすぐにアポを取った知り合いがいたので
仲間に入れて頂きました
直樹さんが伝えていることは、人と人とが出会い、生きていくために必要なこと。
そこに診断名があると忘れがちになってしまう気がする。
先日、髪を切るのが嫌だと言う記事を書きました。
自閉症は感覚過敏があるから切るのが苦手なんだ。
自閉症特有の「こだわり」があるから切れないんだ。
自閉症は変化することが苦手だから切りたくないんだ。
・・・
と、自閉症だから、が付きまとうけど、
でもホントは、ただただ、長い髪が好きなだけかもしれない。
「自閉症だから」にとらわれてしまう自分に気付かせてもらいました。
目の前にいる子が、何が好きで、どう思っているのか。
そこを聞くことができてから、必要な支援を考えて行かなければ
支援の押し付けになってしまうからね。
 今回の講演では、質疑応答の時に
今回の講演では、質疑応答の時に
文字盤ポインティングを使うとハナシコトバとしての表現ができる、という様子がリアルタイムで見ることができました。
このケーブルのおかげです

質疑応答の最初、会場の様子に対するコメントは座布団3枚ものでした
講演の裏方として関われて本当に良かったです。スタッフ弁当も美味しかったし
今回は定員に達してしまうのが早くお断りした方も多かったのが申し訳ないと思いつつ、どこかでまた企画されて長野に来ていただけるといいなと思います。
東田直樹さん。
書籍「自閉症の僕が跳びはねる理由―会話のできない中学生がつづる内なる心
を知ったのはかなり前で、ムクのできなさに落ち込んでいた時期。
重度って言ってもこんな文章を書けるなら軽い方なんだじゃないの?
と。勝手に思い込み読みませんでした。
昨年のNHKドキュメンタリーを観て、なんていう勘違いをしていたのだと反省し、
次の日に「自閉症の僕が跳びはねる理由―会話のできない中学生がつづる内なる心
を購入して読み、涙が止まりませんでした

会いたいな・・・と思っていたら同じように思ってすぐにアポを取った知り合いがいたので
仲間に入れて頂きました

直樹さんが伝えていることは、人と人とが出会い、生きていくために必要なこと。
そこに診断名があると忘れがちになってしまう気がする。
先日、髪を切るのが嫌だと言う記事を書きました。
2015/04/10
自閉症は感覚過敏があるから切るのが苦手なんだ。
自閉症特有の「こだわり」があるから切れないんだ。
自閉症は変化することが苦手だから切りたくないんだ。
・・・
と、自閉症だから、が付きまとうけど、
でもホントは、ただただ、長い髪が好きなだけかもしれない。
「自閉症だから」にとらわれてしまう自分に気付かせてもらいました。
目の前にいる子が、何が好きで、どう思っているのか。
そこを聞くことができてから、必要な支援を考えて行かなければ
支援の押し付けになってしまうからね。
 今回の講演では、質疑応答の時に
今回の講演では、質疑応答の時に文字盤ポインティングを使うとハナシコトバとしての表現ができる、という様子がリアルタイムで見ることができました。
このケーブルのおかげです


質疑応答の最初、会場の様子に対するコメントは座布団3枚ものでした

講演の裏方として関われて本当に良かったです。スタッフ弁当も美味しかったし

今回は定員に達してしまうのが早くお断りした方も多かったのが申し訳ないと思いつつ、どこかでまた企画されて長野に来ていただけるといいなと思います。
相手がネコだとできるのに
 先週、しまの体調が悪くなりました
先週、しまの体調が悪くなりました
また泌尿器系で・・・ストレスを溜めやすい性格なんだね。
前回の経験から、今回は「ん?」と感じるものがあり
早く気が付くことができました。
朝、普段通りに過ごしていたシマが、夕方はトイレに座ったままの時間が長いの。トイレに行く回数も増えて、観察していると座り方もぎこちない。おしっこをみたり、お腹をさわってみたり、あーだこーだと観察しながら思いました。
相手がムクだったら・・・こんなに観察したかな。
コトバで話せない前提で分かってあげようとしたかな。
コトバが片言だった頃は、気持ちや状況を分かってあげようと観察しまくったけど
中学生になってある程度はコトバで話せるようになってくると
「具合悪いなら言ってね」とコトバで伝えるように促しがちになっていたことに気が付き、反省

自分の気持ちや状況をスラスラと説明するのは苦手なのに。
相手がネコだとできるのにね。
佐々木正美先生の講演会にて
先日、佐々木正美先生の講演会がお隣の飯綱町にて開催されました。
NPO法人SUNの10周年記念ということで、参加費無料。
こんな山の中なのに 自閉症支援の世界ではすごい方がいるから呼べるんだよね。
自閉症支援の世界ではすごい方がいるから呼べるんだよね。
長野でお会いできるとは思わなかったので、人のつながりに感謝です!
ちなみに、2010年にも講演会があると聞いて稲荷山養護学校に行ったのですが
体調不良ということでキャンセルに。
5年越しに実現です。
どうしても一番前でお聞きしたかったので一緒に行った友人にも早く出てもらいました
先生の本は沢山読んでいます。
有名なのは今回の演題にもなっていた子どもへのまなざし だと思います。
だと思います。
でも、私が一番初めに読んで気に入っているのは、育てたように子は育つ です。
です。
学生の頃から相田みつをさんの書籍が好きだったので。
今回のお話しも心が休まる時間になりました
一番、心に残っているのは「自分を大切にしている人は、人も大切に生きている」という言葉です。
子どもにも自分を大切に生きて欲しいのであれば、身近にいる私がそう生きないとね。
(現在進行形で、自分を大切に生きている自覚はあるけど )
)
発達障害のある子ども達の特徴も分かりやすくお話ししてくれました。
十人十色の特徴があるので、断言することもなく一言一言丁寧に言葉を選んで話されていたので
じっくりと言葉を味わい、初心に帰ることができました。
本に書かれていることと同じ内容でも、言葉として聞くと新たな感覚になります。
一つだけお話を聞きながら葛藤した時間があります。
それは「親孝行は親より長く生きていること」というお話をされたとき。
我が子が先に亡くなるということは、辛く悲しく耐えがたいことではあるけれど、
正直言って、私はムクより一日でも長く生きていたいと思っています。
今、私がこの世からいなくなったら、ムクは誰かに「助けて」と言えるのだろうか。
困っていること、やりたいことを自ら伝えられるだろうか?
正しく受取ってもらえるだろうか?
お金の管理、身支度、食生活、仕事、近所づきあい、
サポートしてくれる人と出会えるまでは、ムクより先に逝くわけにはいかないの。
そう葛藤しながら出てきた思いは、
「だから、安心して私が先立てるように、今、活動しているんだ」ってこと。
自分の人生には限りがあるのだから、今を大切に生きないとね。
NPO法人SUNの10周年記念ということで、参加費無料。
こんな山の中なのに
 自閉症支援の世界ではすごい方がいるから呼べるんだよね。
自閉症支援の世界ではすごい方がいるから呼べるんだよね。長野でお会いできるとは思わなかったので、人のつながりに感謝です!
ちなみに、2010年にも講演会があると聞いて稲荷山養護学校に行ったのですが
体調不良ということでキャンセルに。
2010/12/16
どうしても一番前でお聞きしたかったので一緒に行った友人にも早く出てもらいました

先生の本は沢山読んでいます。
有名なのは今回の演題にもなっていた子どもへのまなざし
でも、私が一番初めに読んで気に入っているのは、育てたように子は育つ
学生の頃から相田みつをさんの書籍が好きだったので。
今回のお話しも心が休まる時間になりました

一番、心に残っているのは「自分を大切にしている人は、人も大切に生きている」という言葉です。
子どもにも自分を大切に生きて欲しいのであれば、身近にいる私がそう生きないとね。
(現在進行形で、自分を大切に生きている自覚はあるけど
 )
)発達障害のある子ども達の特徴も分かりやすくお話ししてくれました。
十人十色の特徴があるので、断言することもなく一言一言丁寧に言葉を選んで話されていたので
じっくりと言葉を味わい、初心に帰ることができました。
本に書かれていることと同じ内容でも、言葉として聞くと新たな感覚になります。
一つだけお話を聞きながら葛藤した時間があります。
それは「親孝行は親より長く生きていること」というお話をされたとき。
我が子が先に亡くなるということは、辛く悲しく耐えがたいことではあるけれど、
正直言って、私はムクより一日でも長く生きていたいと思っています。
今、私がこの世からいなくなったら、ムクは誰かに「助けて」と言えるのだろうか。
困っていること、やりたいことを自ら伝えられるだろうか?
正しく受取ってもらえるだろうか?
お金の管理、身支度、食生活、仕事、近所づきあい、
サポートしてくれる人と出会えるまでは、ムクより先に逝くわけにはいかないの。
そう葛藤しながら出てきた思いは、
「だから、安心して私が先立てるように、今、活動しているんだ」ってこと。
自分の人生には限りがあるのだから、今を大切に生きないとね。
なぜ、ほめることができるの?
先日、友人から
「私たちの子どもって、ほめるところなんてないじゃん。
どうしてほめることができるの?」
と聞かれて、さて、どーしてだろうと考えました。
答えはただ一つ。
怒るのがめんどくさかったから
怒るとか叱るということは、何かできないことがあってそれをできるようにしないと
社会的に今後、本人が困るだろうから直させないと、と思っているから言うのだと思う。
何度か言ったりやらせてできるようになるならいいけど、
何度言ってもできるようにならない(それが苦手なんだから当然なんだけど)。
言ってもできない、
やって見せてもできない、
そんなことを何度も繰り返しているうちにめんどくさい芽がニョキニョキでてきて、
直させるの、やーめた!
できているところをほめてあげた方が、楽じゃん。
そんな訳で、ムクのできているところをほめるようにしたのは
色々言うのがめんどくさくなった結果なんです。
やって欲しくない行動を見ちゃうと「注意しなくちゃいけない」と思ってしまうので
気が付かないフリをしていたのも注意するのがめんどくさかったから。
今になって「身だしなみはもうちょっとやらせれば良かったかも・・・」と思うけど
それもまた今からでも遅くはないハズ



「私たちの子どもって、ほめるところなんてないじゃん。
どうしてほめることができるの?」
と聞かれて、さて、どーしてだろうと考えました。
答えはただ一つ。
怒るのがめんどくさかったから
怒るとか叱るということは、何かできないことがあってそれをできるようにしないと
社会的に今後、本人が困るだろうから直させないと、と思っているから言うのだと思う。
何度か言ったりやらせてできるようになるならいいけど、
何度言ってもできるようにならない(それが苦手なんだから当然なんだけど)。
言ってもできない、
やって見せてもできない、
そんなことを何度も繰り返しているうちにめんどくさい芽がニョキニョキでてきて、
直させるの、やーめた!
できているところをほめてあげた方が、楽じゃん。
そんな訳で、ムクのできているところをほめるようにしたのは
色々言うのがめんどくさくなった結果なんです。
やって欲しくない行動を見ちゃうと「注意しなくちゃいけない」と思ってしまうので
気が付かないフリをしていたのも注意するのがめんどくさかったから。
今になって「身だしなみはもうちょっとやらせれば良かったかも・・・」と思うけど

それもまた今からでも遅くはないハズ




停電に学ぶ
今朝の新聞を読んで昨日の停電騒ぎがすごく大変なことだたっと知りました。
わが家の周辺だけ?停電してなかったので・・・
停電してなかったので普通に登校したムク。
ユズが充電休みだったので 二人で充電するべく遠出しました。
二人で充電するべく遠出しました。
現地についてすぐ学校からの「お昼を食べずに下校」の緊急一斉メール。
困った!
現地で遊ばず折り返して帰ればユズの充電にはならないし、
かといって、ムクがお昼を食べずにどれだけ待てるか・・・うーん。
そんなことを考えていたらムクから「着いたよ」と電話が。
はやっ!
もしものために家の鍵を開けて帰る練習はしてあったので良かったけど
ご飯を食べる練習も必要だったと実感しました。
今回はお菓子食べ放題を許可して待ってもらいました。
これからのために、お湯を沸かしてカップラーメンを作る練習と
冷凍食品をレンジで温める練習をしてあげよっと。
その前に・・・食材を買いだめしておくことも大事ですね


***
そして充電することになったユズですが、今日は約束通り登校しました。
一年前は、クラスに入れず本人も苦しい思いをしていたんだけど
今回は自分から「こういう理由で辛い」と言えたので成長を感じました。
一つ残念なのは、ユズが去年どんな思いでクラスに入れなくなったのか
どんなクラスの状況だったのかが、校内で情報共有されてなかったこと。
共有されていたら、同じ状況になることを避けられたのにな。
わが家の周辺だけ?停電してなかったので・・・
停電してなかったので普通に登校したムク。
ユズが充電休みだったので
 二人で充電するべく遠出しました。
二人で充電するべく遠出しました。現地についてすぐ学校からの「お昼を食べずに下校」の緊急一斉メール。
困った!
現地で遊ばず折り返して帰ればユズの充電にはならないし、
かといって、ムクがお昼を食べずにどれだけ待てるか・・・うーん。
そんなことを考えていたらムクから「着いたよ」と電話が。
はやっ!
もしものために家の鍵を開けて帰る練習はしてあったので良かったけど
ご飯を食べる練習も必要だったと実感しました。
今回はお菓子食べ放題を許可して待ってもらいました。
これからのために、お湯を沸かしてカップラーメンを作る練習と
冷凍食品をレンジで温める練習をしてあげよっと。
その前に・・・食材を買いだめしておくことも大事ですね



***
そして充電することになったユズですが、今日は約束通り登校しました。
一年前は、クラスに入れず本人も苦しい思いをしていたんだけど
今回は自分から「こういう理由で辛い」と言えたので成長を感じました。
一つ残念なのは、ユズが去年どんな思いでクラスに入れなくなったのか
どんなクラスの状況だったのかが、校内で情報共有されてなかったこと。
共有されていたら、同じ状況になることを避けられたのにな。
紙のテストより大事なコト
最近よく聞いたり目にする「アセスメント」。
何が得意で何に困っているのかというような、
本人に関する情報を収集して分析して評価して課題を見つけて対応策を導くこと。
発達障がいの支援はアセスメントが大事なんだって。
今回WISC-IVをやって頂いたのもそのため。
だから、説明してくれた先生がムクに
「苦手なことは『こうして欲しい』ってお願いしていいんだよ」と伝えてくれたのですが
・
・
・
それができるようになれば、もう心配なんてしませんって。
自分の思っていることを相手に伝えることができるなら。
図形が苦手なのはどうでもいいの。英語だって読めなくてもいい。
なんとなーく、形が分かって、なんとなーく、英語っぽい言葉になっていれば。
テストの点が低くても本人が苦にしてないからね。
それより大事なのは、伝える力だと思う。
自分の「こうしたい」や「こうして欲しい」を伝える力は付けて欲しい。
それが、ムクにとって一番の苦手分野なんだけど。
今は困ったような笑顔で切り抜けられても、社会にでたらそうはいかないと思う。
支援級の友達からも、「ムクくんさー返事しないよ」とか「話が続かない」とか
私に言ってくれる子もいるくらいだもの。
お喋りは好きで、好きなことは話すけど会話にはなってないらしい
家で「こうして欲しい」と言う練習をしたことはできるようになったので
支援級でも会話を練習する時間があるといいのにな。
そこまで求めるのは欲張りかなと思ったけど、巡回相談の先生には希望を伝えました
上手く伝わるといいな~
何が得意で何に困っているのかというような、
本人に関する情報を収集して分析して評価して課題を見つけて対応策を導くこと。
発達障がいの支援はアセスメントが大事なんだって。
今回WISC-IVをやって頂いたのもそのため。
だから、説明してくれた先生がムクに
「苦手なことは『こうして欲しい』ってお願いしていいんだよ」と伝えてくれたのですが
・
・
・
それができるようになれば、もう心配なんてしませんって。
自分の思っていることを相手に伝えることができるなら。
図形が苦手なのはどうでもいいの。英語だって読めなくてもいい。
なんとなーく、形が分かって、なんとなーく、英語っぽい言葉になっていれば。
テストの点が低くても本人が苦にしてないからね。
それより大事なのは、伝える力だと思う。
自分の「こうしたい」や「こうして欲しい」を伝える力は付けて欲しい。
それが、ムクにとって一番の苦手分野なんだけど。
今は困ったような笑顔で切り抜けられても、社会にでたらそうはいかないと思う。
支援級の友達からも、「ムクくんさー返事しないよ」とか「話が続かない」とか
私に言ってくれる子もいるくらいだもの。
お喋りは好きで、好きなことは話すけど会話にはなってないらしい

家で「こうして欲しい」と言う練習をしたことはできるようになったので
支援級でも会話を練習する時間があるといいのにな。
そこまで求めるのは欲張りかなと思ったけど、巡回相談の先生には希望を伝えました

上手く伝わるといいな~
本田秀夫先生の講演会を聞いて
広報する間もなく終わったイベント。
長野市障害ふくしネット(自立支援協議会)秋の全体会『発達障害を考える』。
第一部は、信州大学病院子どものこころ診療部の本田秀夫先生の講演会でした。
第二部は「当事者が語る」ということで成人になってから発達障害と診断された方と
保護者・・・ということで、一緒に登壇させていただきました。
チラシ配布した後に依頼が来るって・・・どーなの?とか思いながら
本田先生のお話は、直前に読んでいた本がとても良かったので楽しみにしていました
講演の内容も本と同じだったので、安心して聴くことができました。
どんな内容かは本を読んでね
何が良かったのか。
正直に言うと、
これまでの子育てを褒めてもらった感じがするから
ムクは学校で暴れることもなく、喧嘩することもなく、大声を出すこともなく、泣くこともなく、
宿題を嫌がることもなく、とっても大人しい
だから、楽だよね。
だから、言うことを聞いてくれるんだよね。
と、思われがちです。
でも、就学前まではそれなりに大変だった。
療育手帳がすぐにもらえるくらいの自閉っ子だったんだもの。
本田先生がお話した
「片付けは最初に手伝う」も「欲しがるようなものは見せない」も「楽しかった経験」も
就学前からやってきたし、こだわりにもとことん付き合ってきました。
トミカを並べさせたら私の方が上手にできたし
今でもVS嵐のこだわりだけは大事にしてあげている。
だから信頼されているんだと気付かせてもらえました。
もちろん私一人ではなく、
家族も出会った先生もみんなムクのことを温かく見守ってくれたから今があるんだよね。
第二部で当事者の方が最後に言われた
「親に味方になって欲しかった」
この言葉も心に残りました。
残念だけど、まだまだ当事者や保護者の味方は少ないと思う。
ムクの味方はもちろんだけど、
発達が気になる子どもやその保護者の味方になって仲間を増やしたいと思いました
本田先生の講演で残念だったのは、時間がなくて最後の
「インターフェースのある支援システム」についてが聞けなかったこと。
どこか別の機会で聞くことができるといいな。
***** お知らせ *****
長野市障害ふくしネット(自立支援協議会)秋の全体会『発達障害を考える』。
第一部は、信州大学病院子どものこころ診療部の本田秀夫先生の講演会でした。
第二部は「当事者が語る」ということで成人になってから発達障害と診断された方と
保護者・・・ということで、一緒に登壇させていただきました。
チラシ配布した後に依頼が来るって・・・どーなの?とか思いながら

本田先生のお話は、直前に読んでいた本がとても良かったので楽しみにしていました

講演の内容も本と同じだったので、安心して聴くことができました。
どんな内容かは本を読んでね

何が良かったのか。
正直に言うと、
これまでの子育てを褒めてもらった感じがするから

ムクは学校で暴れることもなく、喧嘩することもなく、大声を出すこともなく、泣くこともなく、
宿題を嫌がることもなく、とっても大人しい
だから、楽だよね。
だから、言うことを聞いてくれるんだよね。
と、思われがちです。
でも、就学前まではそれなりに大変だった。
療育手帳がすぐにもらえるくらいの自閉っ子だったんだもの。
本田先生がお話した
「片付けは最初に手伝う」も「欲しがるようなものは見せない」も「楽しかった経験」も
就学前からやってきたし、こだわりにもとことん付き合ってきました。
トミカを並べさせたら私の方が上手にできたし

今でもVS嵐のこだわりだけは大事にしてあげている。
だから信頼されているんだと気付かせてもらえました。
もちろん私一人ではなく、
家族も出会った先生もみんなムクのことを温かく見守ってくれたから今があるんだよね。
第二部で当事者の方が最後に言われた
「親に味方になって欲しかった」
この言葉も心に残りました。
残念だけど、まだまだ当事者や保護者の味方は少ないと思う。
ムクの味方はもちろんだけど、
発達が気になる子どもやその保護者の味方になって仲間を増やしたいと思いました

本田先生の講演で残念だったのは、時間がなくて最後の
「インターフェースのある支援システム」についてが聞けなかったこと。
どこか別の機会で聞くことができるといいな。
***** お知らせ *****
2014/10/15
初めての文化祭
昨日、一昨日は中学校入学して初めての文化祭でした
いつもと違うスケジュール。
何をやるのか分からないことへの不安と怒り。
一か月前から休むことを宣言していたムクですが一日目だけは登校しました。
二日目は吹奏楽部の発表と音楽会。
体育館に鳴り響く楽器の音が耐えられないほど苦痛なのは知っているので休ませました。
(決して、お弁当を作らなくて済む と思ったわけでは・・・
と思ったわけでは・・・ )
)
 ムクのクラスの発表です♪
ムクのクラスの発表です♪
本人不在のクラス発表ってのも・・・
ムクが休んでいる理由がどう伝わっているのか分からないけど、「反響する音が苦手だから」という理由が伝わっていたとしても、「一緒に参加して団結しよう!」とかクラスから強要されても困るし、かといって休んでいることさえも気にされてないのも寂しいものです。元気だけど休むことに対して担任の先生から何の連絡もないからね。
支援級に在籍しているから、原級ってのは関係ないのかな~
小学校の時は、本人に寄り添いながらなるべく行事に参加できるよう配慮してきましたが
中学校でそれは必要ないなと感じています。
本人が選べるようになったので、行事参加は本人に選んでもらうってことで。
合唱の曲名が決まってからは毎日毎日、
家に帰ると各クラスの曲名をYouTubeで検索して一人で歌って、一人で指揮している姿を見ていると
歌うことは好きなんだな~と思います。
それくらい好きだけど、音の事を考えて欠席することを選んだムクの本当の気持ちはどうなんだろう。
と、親としてはセンチメンタルな気分になりましたが、
当の本人は「おわったー 」とすでに過去の話になっています。
」とすでに過去の話になっています。
気持ちの切り替えが早いってのは素晴らしい。

いつもと違うスケジュール。
何をやるのか分からないことへの不安と怒り。
一か月前から休むことを宣言していたムクですが一日目だけは登校しました。
二日目は吹奏楽部の発表と音楽会。
体育館に鳴り響く楽器の音が耐えられないほど苦痛なのは知っているので休ませました。
(決して、お弁当を作らなくて済む
 と思ったわけでは・・・
と思ったわけでは・・・ )
) ムクのクラスの発表です♪
ムクのクラスの発表です♪本人不在のクラス発表ってのも・・・
ムクが休んでいる理由がどう伝わっているのか分からないけど、「反響する音が苦手だから」という理由が伝わっていたとしても、「一緒に参加して団結しよう!」とかクラスから強要されても困るし、かといって休んでいることさえも気にされてないのも寂しいものです。元気だけど休むことに対して担任の先生から何の連絡もないからね。
支援級に在籍しているから、原級ってのは関係ないのかな~
小学校の時は、本人に寄り添いながらなるべく行事に参加できるよう配慮してきましたが
中学校でそれは必要ないなと感じています。
本人が選べるようになったので、行事参加は本人に選んでもらうってことで。
合唱の曲名が決まってからは毎日毎日、
家に帰ると各クラスの曲名をYouTubeで検索して一人で歌って、一人で指揮している姿を見ていると
歌うことは好きなんだな~と思います。
それくらい好きだけど、音の事を考えて欠席することを選んだムクの本当の気持ちはどうなんだろう。
と、親としてはセンチメンタルな気分になりましたが、
当の本人は「おわったー
 」とすでに過去の話になっています。
」とすでに過去の話になっています。気持ちの切り替えが早いってのは素晴らしい。
逢えてよかったと言われて

昨日は「今日からできる シンプル子育てコーチング」の最終日でした
 毎回、その時が必要な方と出会えたような気がします。
毎回、その時が必要な方と出会えたような気がします。内容は本当に簡単で「いまさらそんなこと」と思われるくらい簡単だけど、そんな簡単なことを行動するだけで子育てが変れるし、参加者の方の思い描いた子育てに変っていくといいな、と思います。
参加して頂いた皆さま、ありがとうございました

そんな日に嬉しいことがありました

毎週木曜日は、にじいろキッズらいふの電話相談窓口として在中しているのですが、
以前、私の体験談を聞いた先生から「しまりーさんに会ってみたら」と言われたとのことで
私を訪ねてきてくれた方がいました。
講座中だったので長い時間はお話しできませんでしたが、別れた後に
「逢えてよかった」と言って頂き、
私も色々と考えていたことがスッキリしました。
色々な専門家に相談してアドバイスをもらっているうちに
子育てに自信がなくなったり、こんがらがったりすることがあると思う。
私は専門家じゃないから・・・と相談を受けることに遠慮があったけど
専門家じゃないから、こんがらがった子育てを解きほぐすことができるんじゃないかな~と。
それに、子どもの障害を受け入れるまでは、感情も揺れる。
認めたくないし、治ると思いたい。特に、診断がつくかつかないかグレーの子はね。
そういったお子さんを育てている方への支援(と啓発)が必要だと思うので
個別相談、はじめます。
これまでの経験と学びとつながりをすべて提供するので有料で。
どうやっていくかは・・・昨日、思ったばかりなのでこれから考えます

二学期中間テストがやってくる
今週末は中学校の文化祭。
来週末は二学期の中間テストです
そろそろ勉強をした方がいいんじゃないかとお誘いし、付き合いました。
本人の希望で「理科」からね。
問題。
かおりさんは家の台所にあった3つの白い粉末の物質A~Cが何であるか調べるため、
それぞれの物質をフライパンで加熱した。その結果、物質A,Bは黒く焦げた。
物質Cはパチパチとはねたが燃えなかった。3つの物質A~Cは、砂糖、小麦粉(でんぷん)
食塩のいずれかである。
この文章の後に問いが書いてあるんだけど、
(5)物質Cは何か?の答えが「炭素」って・・・

これが、文章問題の意味が分からない、ってヤツですね。
「3つの物質A~Cは、砂糖、小麦粉(でんぷん)、食塩のいずれかである」と書いてあれば
暗黙のルールで3つの中から選ぶんだな、と判断するよね。大多数は。
ムクは、最初の長い文章が状況を説明しているとは思わないからな。
最初の長い文章が読めなくても、問題の出し方が
(5)A~Cの物質を線で結びなさい
A 砂糖
B 小麦粉(でんぷん)
C 食塩
とか
(5)物質Cは「砂糖、小麦粉(でんぷん)、食塩」のどれでしょうか
だったら、きっと分かるんだろうな~
上のように、「物質Cは砂糖、小麦粉(でんぷん)、食塩どれだ」と聞いたら正解したからね。
ムクの様子を見ていると
本人の理解力に合わせたテスト問題を出してもらえるといいのにな、と思ってしまう。
頑張って勉強した結果、ちょこっと点数が上がる経験って大事だし、させたいよ。
ムクが原級と同じ内容を勉強して、同じ内容のテストを受けるのは、
「検事に合格する」ことを目的とした生活を余儀なくされ、
強制的に司法書士の勉強をさせられているような感じがする。
あー想像しただけで、ムリムリムリ 生きた心地しない
生きた心地しない
ま、HEROの最終回を観た後だから、そう思うのかも(笑)
「単元ごとにテストがあれば覚えていられるのに」と言ったムクの言葉が離れません。
来週末は二学期の中間テストです

そろそろ勉強をした方がいいんじゃないかとお誘いし、付き合いました。
本人の希望で「理科」からね。
問題。
かおりさんは家の台所にあった3つの白い粉末の物質A~Cが何であるか調べるため、
それぞれの物質をフライパンで加熱した。その結果、物質A,Bは黒く焦げた。
物質Cはパチパチとはねたが燃えなかった。3つの物質A~Cは、砂糖、小麦粉(でんぷん)
食塩のいずれかである。
この文章の後に問いが書いてあるんだけど、
(5)物質Cは何か?の答えが「炭素」って・・・


これが、文章問題の意味が分からない、ってヤツですね。
「3つの物質A~Cは、砂糖、小麦粉(でんぷん)、食塩のいずれかである」と書いてあれば
暗黙のルールで3つの中から選ぶんだな、と判断するよね。大多数は。
ムクは、最初の長い文章が状況を説明しているとは思わないからな。
最初の長い文章が読めなくても、問題の出し方が
(5)A~Cの物質を線で結びなさい
A 砂糖
B 小麦粉(でんぷん)
C 食塩
とか
(5)物質Cは「砂糖、小麦粉(でんぷん)、食塩」のどれでしょうか
だったら、きっと分かるんだろうな~
上のように、「物質Cは砂糖、小麦粉(でんぷん)、食塩どれだ」と聞いたら正解したからね。
ムクの様子を見ていると
本人の理解力に合わせたテスト問題を出してもらえるといいのにな、と思ってしまう。
頑張って勉強した結果、ちょこっと点数が上がる経験って大事だし、させたいよ。
ムクが原級と同じ内容を勉強して、同じ内容のテストを受けるのは、
「検事に合格する」ことを目的とした生活を余儀なくされ、
強制的に司法書士の勉強をさせられているような感じがする。
あー想像しただけで、ムリムリムリ
 生きた心地しない
生きた心地しない
ま、HEROの最終回を観た後だから、そう思うのかも(笑)
「単元ごとにテストがあれば覚えていられるのに」と言ったムクの言葉が離れません。
プラスにあきらめる
先日、ある支援者の方に「ムク君もお母さんも自己肯定感があって素晴らしい」と
褒めて頂きました。確かに、母子ともに根拠のない自信はあります
でも、なんとなく違うんだよね~でも、そうなのかな~でもな~と思いながら入った本屋さんで
嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え
をみつけ、何気に開いたページに書いてあったのが「肯定的にあきらめる」
これだ!
ムクと向き合う時は「プレスにあきらめる」と決めています。
「あきらめる」というと、できないから本人の将来に期待していないようだけど、そうじゃない。
それがムクだから、と思うこと。
テストで5教科60点だとしても、「60点なんだ」で終わり。
「せめて5教科で100点取れるように残りの40点をどうやって勉強するか」とは考えない。
足りないところをみるのではなく、「60点を取れた」という事実を受け取る。
そういうのを「自己受容」と言うようです。
なるほど 自己受容は大事だね。
自己受容は大事だね。
私も自己受容(+根拠のない自信)を大事にしていこうと思います。
人前でお話する機会を頂くことがありますが、実は苦手です。
上手く話せないし、緊張するし、役に立てたか気になるし、終わると反省しまくる。
でも、また引き受けます。
喋るのが下手でも緊張しても、それが自分だから

今まで「自己肯定感」という言葉が流行っていたけど(たぶん)
これからは「自己受容」が流行りの言葉になる予感。
褒めて頂きました。確かに、母子ともに根拠のない自信はあります

でも、なんとなく違うんだよね~でも、そうなのかな~でもな~と思いながら入った本屋さんで
嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え
をみつけ、何気に開いたページに書いてあったのが「肯定的にあきらめる」
これだ!
ムクと向き合う時は「プレスにあきらめる」と決めています。
「あきらめる」というと、できないから本人の将来に期待していないようだけど、そうじゃない。
それがムクだから、と思うこと。
テストで5教科60点だとしても、「60点なんだ」で終わり。
「せめて5教科で100点取れるように残りの40点をどうやって勉強するか」とは考えない。
足りないところをみるのではなく、「60点を取れた」という事実を受け取る。
そういうのを「自己受容」と言うようです。
なるほど
 自己受容は大事だね。
自己受容は大事だね。私も自己受容(+根拠のない自信)を大事にしていこうと思います。
人前でお話する機会を頂くことがありますが、実は苦手です。
上手く話せないし、緊張するし、役に立てたか気になるし、終わると反省しまくる。
でも、また引き受けます。
喋るのが下手でも緊張しても、それが自分だから


今まで「自己肯定感」という言葉が流行っていたけど(たぶん)
これからは「自己受容」が流行りの言葉になる予感。
嬉しかったハナシ
ユズの好きそうな本棚を作るワークショップがあったので行ってきました。
本物の壁を塗るペンキ塗りを喜んでやってました
嬉しかったハナシはそれじゃなくて。
一緒に参加された方の一言が、とっても嬉しかったんです。
ムクは手が汚れるペンキ塗りには興味がないので
部屋の片隅でふなっしーの口調で独り言を言い続けていた時に
「オープンマインドでいいですね」と。
これが、怪訝そうに見られたら「いや、実は障害があって…」と
説明する流れになるんだけど、受け取り側が柔軟な方だと
ムクを障害児にしなくてもいいんだなーと実感しました。
障害とは社会生活の中で活動や参加が制限されている状態をいう
と、聞いた記憶があります。ホントにそうだね。
今夜は24時間テレビですが…
ダンスも歌もテレビのネタになるようなことには挑戦しないムクだけど、
朝起きて学校に行って宿題やって余暇して寝る毎日が挑戦だったりするのかなー
と、眠れない夜に書いてみました
本物の壁を塗るペンキ塗りを喜んでやってました

嬉しかったハナシはそれじゃなくて。
一緒に参加された方の一言が、とっても嬉しかったんです。
ムクは手が汚れるペンキ塗りには興味がないので
部屋の片隅でふなっしーの口調で独り言を言い続けていた時に
「オープンマインドでいいですね」と。
これが、怪訝そうに見られたら「いや、実は障害があって…」と
説明する流れになるんだけど、受け取り側が柔軟な方だと
ムクを障害児にしなくてもいいんだなーと実感しました。
障害とは社会生活の中で活動や参加が制限されている状態をいう
と、聞いた記憶があります。ホントにそうだね。
今夜は24時間テレビですが…
ダンスも歌もテレビのネタになるようなことには挑戦しないムクだけど、
朝起きて学校に行って宿題やって余暇して寝る毎日が挑戦だったりするのかなー
と、眠れない夜に書いてみました

出生前診断について考える
信濃毎日新聞で取り上げている「出生前診断」。
コーチ仲間のゆーみんが
この問題については、一人ひとり深く考えることが大事で、
個々の意見どれも尊重されるものだと思います。
とブログに書いていたので、私も考えてみました。
ゆーみんのブログはこちら ⇒ コーチング☆ Being-yuming-coaching!



出生前診断の記事を読んだ時に
障害があるかもしれない子どもを授かったときに産むか産まないか・・・
さあ、あなたはどうする?
という決断を親ができるようになった、ってことか、と思いました。
医学の進歩はありがたいことだけどめんどうでもあるな、それが直感です。
ぷれジョブの活動をするようになって、ダウン症のお子さんがいるお母さんと出会い
ダウン症ってそうなんだーと、まだまだ未知の世界だけど知ることができました。
ムクが発達障害でなければ、今のような充実した生活はしていないだろうし
沢山の方と出逢え、沢山の学びがあったのは、ムクが障害児だったからで、
そう思うと、障害があっても産んで良かったと思う時もあれば
日常生活のひとつひとつを何度も何度も怒らないように教え、
学校の宿題をフォローし、それでも、できるようにならなかったり言葉が通じないときは
産まなきゃ良かったと思う時もある。
ゆれる~~
障害のある子を育てる、とか
障害を受け入れる、とか、そう簡単にできることじゃないよ。
だって大変だもの。
出生前診断の議論をする前に・・・
陽性だったときに中絶を選択するのは自由なのだから、選択した理由を聞いてほしいな。
経済的、きょうだい(姉兄)がいる、親戚に顔向けできない、地域が冷たい
学校に通えるか心配、就職できない、一生面倒をみるのが不安
理由は一つじゃない。
でも「ある」ハズ。
そこで出てきた悩みを解決することが先ではないかと思ってしまう。
障害のある子を産んでも、何一つ困らずに育てられる地域社会があって
その上で、出生前診断の議論をするなら分かるんだけどね。
親の気持ちは人それぞれだよね、で終わって欲しくない。
信濃毎日新聞のまとめに期待したいです。
コーチ仲間のゆーみんが
この問題については、一人ひとり深く考えることが大事で、
個々の意見どれも尊重されるものだと思います。
とブログに書いていたので、私も考えてみました。
ゆーみんのブログはこちら ⇒ コーチング☆ Being-yuming-coaching!



出生前診断の記事を読んだ時に
障害があるかもしれない子どもを授かったときに産むか産まないか・・・
さあ、あなたはどうする?
という決断を親ができるようになった、ってことか、と思いました。
医学の進歩はありがたいことだけどめんどうでもあるな、それが直感です。
ぷれジョブの活動をするようになって、ダウン症のお子さんがいるお母さんと出会い
ダウン症ってそうなんだーと、まだまだ未知の世界だけど知ることができました。
ムクが発達障害でなければ、今のような充実した生活はしていないだろうし
沢山の方と出逢え、沢山の学びがあったのは、ムクが障害児だったからで、
そう思うと、障害があっても産んで良かったと思う時もあれば
日常生活のひとつひとつを何度も何度も怒らないように教え、
学校の宿題をフォローし、それでも、できるようにならなかったり言葉が通じないときは
産まなきゃ良かったと思う時もある。
ゆれる~~
障害のある子を育てる、とか
障害を受け入れる、とか、そう簡単にできることじゃないよ。
だって大変だもの。
出生前診断の議論をする前に・・・
陽性だったときに中絶を選択するのは自由なのだから、選択した理由を聞いてほしいな。
経済的、きょうだい(姉兄)がいる、親戚に顔向けできない、地域が冷たい
学校に通えるか心配、就職できない、一生面倒をみるのが不安
理由は一つじゃない。
でも「ある」ハズ。
そこで出てきた悩みを解決することが先ではないかと思ってしまう。
障害のある子を産んでも、何一つ困らずに育てられる地域社会があって
その上で、出生前診断の議論をするなら分かるんだけどね。
親の気持ちは人それぞれだよね、で終わって欲しくない。
信濃毎日新聞のまとめに期待したいです。
小学校の卒業式
 でした。
でした。すっかり記憶から消えそうですが


ムクの学校は卒業生がひな壇になって対面で座ります。それならムクの様子が見れるかな~と思ったら・・・ひな壇でも前の子に隠れていました

卒業式と言ったら合唱です♪
1年生の頃から3月になると毎日毎日ムクは一人で歌っていたので、やっと本物を聞くことができました
 記念にiPhoneで録音♪
記念にiPhoneで録音♪教室に戻るとハプニング!
先生から一人づつプレゼントを頂きながら応援コメントをもらうときにムクが泣いていたんです

感情を表に出すことがあまりないので、ムクが感情を出したことに感動

卒業式の緊張から解放されたのと
先生や友達とのお別れが寂しいのと
訳のわからない「中学校」という場所に行くことの不安が入り混じったのかな。
そう思うと、ひな壇でムクが見れなかったときは「あー、前にしてもらえればなー
 」と思いましたが
」と思いましたがそれは親の想いであり、ムクにとっては前が見えなくて良かったかもね。
6年間、大変よくがんばりました

中学校は不安のかたまりだよね。
初めての場所、初めての先生、初めてのルール、初めての友達・・・
成長と共に、自分が他の友達と「違う」ということにも気が付くよね。
「変わってる」と言われるかもしれない。
「違う」ことはマイナスじゃないんだよ。
「変わってる」って最高の褒め言葉なんだよ。
ムクはムクのままでいいんだよ。
「変わってる」って最高の褒め言葉なんだよ。
ムクはムクのままでいいんだよ。
祝☆卒業
例年より成長を感じるのはまた1年生になるから?
季節の変わり目は子どもの成長を感じる季節でもあります
今年はいつもより成長を感じるのはなぜだろう?と思ったら
また1年になるからかなーと。中学のね

小学校1年生の時は
給食着のボタンができずにマジックテープで留めたけど今はできるようになったとか
ランドセルを一人で背負えなかったのが、今ではねじれつつも一人でできるとか
私がすべて着替えさせていたけど、今は前後左右裏表は違えども 一人で着替えているとか
一人で着替えているとか
思い返すとできるようになったことが沢山
完ぺきを求めたら「できない」の判定だろうけどね。
雰囲気も場所も人も想像できない新しい環境に行くのだから
手抜きができるところは手を抜いて、
努力は必要だけど今ある力でできる範囲を頑張れば十分だと思う。
(今日の勉強会でも講師の先生が同じコトをお話していたモン♪)
小学校1年生のときは給食着をマジックテープにしたのが
中学校1年生のときは学ランをマジックテープにするだけだよ。
マジックテープの色も白から黒に変るけどね~
今日は最後の授業&給食。
楽しさを満喫してきますように



今年はいつもより成長を感じるのはなぜだろう?と思ったら
また1年になるからかなーと。中学のね


小学校1年生の時は
給食着のボタンができずにマジックテープで留めたけど今はできるようになったとか
ランドセルを一人で背負えなかったのが、今ではねじれつつも一人でできるとか
私がすべて着替えさせていたけど、今は前後左右裏表は違えども
 一人で着替えているとか
一人で着替えているとか思い返すとできるようになったことが沢山

完ぺきを求めたら「できない」の判定だろうけどね。
雰囲気も場所も人も想像できない新しい環境に行くのだから
手抜きができるところは手を抜いて、
努力は必要だけど今ある力でできる範囲を頑張れば十分だと思う。
(今日の勉強会でも講師の先生が同じコトをお話していたモン♪)
小学校1年生のときは給食着をマジックテープにしたのが
中学校1年生のときは学ランをマジックテープにするだけだよ。
マジックテープの色も白から黒に変るけどね~
今日は最後の授業&給食。
楽しさを満喫してきますように



小学校生活最後の参観日☆でした
一年の締めくくりの参観日は学習発表会です。
小学校生活最後の学習発表会の司会をすることになったムク。
緊張して嫌がるかと思ったら「やりたいの 」って。
」って。
進行内容を書いた紙を握りしめ、
発表したグループが座るのを確認してから次を紹介するなど
落ち着いて司会進行していました
その後は謝恩会の意味を含んだお別れ会です。
私はお別れ会の係だったので、仕込んだ企画がうまく進行するか
飲食用に選んだパンが気に入ってもらえるか・・・などなど気になって気になって。
この人だれだ?クイズも子ども達は楽しそうに参加してくれたし
先生へのサプライズ企画も目標通り先生を泣かせることができたし
育ちざかりの6年生にパンは好評でその場でガッツリ食べてくれたし
お別れ会が終わった瞬間に脱力。
その瞬間にムクの頑張った司会の姿もふっとびました



今回、一緒の係になったお母さん方がとても行動力があって発想力もあって、
楽しく準備ができて良かったです。
ムクのカウントダウンによると、卒業式まであと10日。
学生服のお直ししなくちゃ!!!
小学校生活最後の学習発表会の司会をすることになったムク。
緊張して嫌がるかと思ったら「やりたいの
 」って。
」って。進行内容を書いた紙を握りしめ、
発表したグループが座るのを確認してから次を紹介するなど
落ち着いて司会進行していました

その後は謝恩会の意味を含んだお別れ会です。
私はお別れ会の係だったので、仕込んだ企画がうまく進行するか
飲食用に選んだパンが気に入ってもらえるか・・・などなど気になって気になって。
この人だれだ?クイズも子ども達は楽しそうに参加してくれたし
先生へのサプライズ企画も目標通り先生を泣かせることができたし

育ちざかりの6年生にパンは好評でその場でガッツリ食べてくれたし
お別れ会が終わった瞬間に脱力。
その瞬間にムクの頑張った司会の姿もふっとびました




今回、一緒の係になったお母さん方がとても行動力があって発想力もあって、
楽しく準備ができて良かったです。
ムクのカウントダウンによると、卒業式まであと10日。
学生服のお直ししなくちゃ!!!
1日だけの学級閉鎖
2014/02/19
という記事を書きました。
書いたときは「ない」と思っていた学級閉鎖に今日なりました
 1日だけね
1日だけね
そしてムクだけ登校です♪
「朝から支援級に行ける!」と張り切って登校していきました。
1年生のときは学校が嫌で発熱してなんとか登校していたのにね。
ムクにとって学校は楽しい場所です。
学校ってそういう場所であって欲しいですね。
卒業式まであと17日。
カウントダウンの始まりです。
取材される側になって初心に帰る
毎年4月2日が世界自閉症啓発デー
2日~8日までが発達障害啓発週間です。
今年もやります啓発活動!
ってことで、
JDDネットワークながの主催 2014発達障害啓発週間「結」プロジェクト
http://jddnagano.jimdo.com/
に関わってます。
それに関連して取材される側になりました。
子育てで大変なのにお金にもならず、
逆にガソリン代使ってまで活動しているのはナゼ?って改めて聞かれると
そーなんだよねー、なんでやっているんだろー
と初心に帰ることができました。
同じような子どもを育てている人を知らないから一人で悩んでいたり
発達障害(自閉症)について知らないから将来を悲観したり
子どもの行動の意味を知らないから親子で困っていたり
そんな過去があるから知るって大事だな、と思う。
この活動をすることで社会全体に理解してもらおうなんて思っていなくて
隣に座った人や立ち止まった人、学校や地域で出会った人に知ってもらうこと。
それが大事なんだと思う。
ちょっとメンドクサイことになって投げ出してしまいたい思いもあるけれど
そんな小さな活動でも何年かしたら社会全体で理解してもらえるようになって
啓発活動なんてやらなくてもいいようになれば、いいな。
そして初心に帰り・・・
来年は昨年までのように一人で便乗企画をするんだろうな。
2日~8日までが発達障害啓発週間です。
今年もやります啓発活動!
ってことで、
JDDネットワークながの主催 2014発達障害啓発週間「結」プロジェクト
http://jddnagano.jimdo.com/
に関わってます。
それに関連して取材される側になりました。
子育てで大変なのにお金にもならず、
逆にガソリン代使ってまで活動しているのはナゼ?って改めて聞かれると
そーなんだよねー、なんでやっているんだろー
と初心に帰ることができました。
同じような子どもを育てている人を知らないから一人で悩んでいたり
発達障害(自閉症)について知らないから将来を悲観したり
子どもの行動の意味を知らないから親子で困っていたり
そんな過去があるから知るって大事だな、と思う。
この活動をすることで社会全体に理解してもらおうなんて思っていなくて
隣に座った人や立ち止まった人、学校や地域で出会った人に知ってもらうこと。
それが大事なんだと思う。
ちょっとメンドクサイことになって投げ出してしまいたい思いもあるけれど
そんな小さな活動でも何年かしたら社会全体で理解してもらえるようになって
啓発活動なんてやらなくてもいいようになれば、いいな。
そして初心に帰り・・・
来年は昨年までのように一人で便乗企画をするんだろうな。